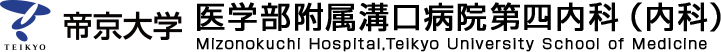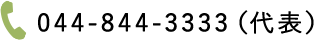肝臓・感染症
当グループの紹介
肝臓領域ではC型慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療、B型慢性肝炎に対する核酸アナログ製剤による治療に加え、原発性胆汁性管炎、自己免疫性肝炎、脂肪性肝疾患の診断と治療などを行っています。
感染症領域では全科からコンサルテーションを受け対応しています。またInfection Control Teamの一員として院内感染防止対策にも取り組み、疫学調査、手指衛生の徹底、抗菌薬の適正使用なども行っています。
呼吸器グループに属し、入院患者さんへの対応も行なっています。
当グループの特色
平成30年度から施行された内科専門医制度に則り、人間味に溢れ知的好奇心を持つ内科専門医を育成します。サブスペシャリティ領域で肝臓専門医、消化器病専門医の取得を指導します。
感染症は横断的であるため、サブ・サブスペシャリティ領域で感染症専門医取得を指導し、感染症学に強い肝臓内科医や消化器内科医のみならず、感染症学に強い循環器内科医、血液内科医、腎臓内科医、呼吸器内科医、内分泌代謝・糖尿病内科医を育成します。
また大学院主科目「肝臓免疫代謝学」を主宰し、学位論文の指導も行っています。
あつかう疾患
1) 肝疾患領域
ウイルス性慢性肝炎と自己免疫性肝疾患の診断と治療、脂肪性肝疾患を通じたメタボリックシンドロームの診療に力を入れています。急性肝炎、肝硬変、肝腫瘍の診療は消化器内科が主体で行い、当グループも協力しています。
2) 感染症領域
細菌、ウイルス、真菌による感染症の診療、加齢や糖尿病によるcompromised hostの感染予防などを行っています。またInfection Control Teamの一員としてカテーテル関連血流感染症や針刺し事故の対策、疫学調査、抗菌薬の適正使用などに取り組んでいます。
3) 総合内科領域
カンファレンスを通じ他のグループと協調してプライマリケアの実践、高齢化社会おけるフレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニアの対策、さらにリハビリテーション科と帝京大学老人保健センター慈宏之里と共に総合支援体制の構築にも努めています。
研究について
1) 臨床医の研究は、1人の患者さんの診療から始まる。
研究は臨床的疑問の解決手段です。患者さんを診察しプロブレムリストをあげ、上級医の指導、カンファレンスでの議論、文献検索により解決して行く、そのような日々の職務から臨床研究は始まります。
2) 臨床研究とは?
臨床研究には観察研究(症例報告、症例対照研究など)と介入研究(ランダム化比較試験など)があります。それらを通じて臨床医の実力をアップしていくことができます。臨床研究を進めていくと、その疾患がどこまで解明されているのか、何が分かっていないのかが判明します。それが臨床の壁です。
3) 基礎研究とは?
臨床の壁を打破するためには基礎研究が必要です。大学院生は臨床研究のみならず基礎研究にも携わり、学外の研究者とのミーティングにも参加し多くの刺激を受け、研究成果を学位論文にまとめることで新たな検査・治療を生むことができ、自身も幅広い視野を持った臨床医になることができます。学位取得はゴールではなく新たなスタートです。「僕は、私は、帝京大学で何をやった。」という誇りを胸に持ち、社会に貢献する医師になって欲しいと思っています。
4) 肝臓免疫代謝学の研究内容
当院に自己免疫性肝疾患の教室を築いた宮川 浩先生の研究を継承し、帝京大学大学院医学研究科において器官系統病態学分野「肝臓免疫代謝学」を主宰しています。肝臓・感染症だけではなく内科学領域の全般を免疫学的・代謝学的アプローチにより研究しています。
業績
-
定期刊行書(学術雑誌)
英文
- Fujioka H, Kikuchi K, Nakahara T, Yoshioka S, Kawai R, Kajitani M, Ishizuka M, Akiyama M, Tanaka Y, Kobayashi A, Sato K, Karube K, Tanaka G, Kohyama T. Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma Developed During Treatment with PD-L1 Inhibitor for Lung Cancer. Internal Medicine 2025;Mar 8. doi: 10.2169/internalmedicine.5114-24.
- Takeuchi A, Abe M, Furukawa S, Namisaki T, Takahashi A, Abe K, Kikuchi K, Miura R, Tachizawa N, Takaki A, Ueno Y, Honda A, Terai S, Komori A, Ohira H, Yoshiji H, Yonezawa A, Tanaka A. Validation of PBC-10 in Japanese patients with primary biliary cholangitis. Hepatology Research 2025;Apr 26. doi: 10.1111/hepr.14199.
- Matsumoto K, Doi S, Adachi T, Watanabe A, Katsukura N, Tsujikawa T, Aso T, Takahashi T, Kikuchi K. Surface Area Outcomes in EUS-Guided Liver Biopsy: A Comparative Study of Franseen and Fork-tip Needles. BMC Gastroenterology 2025;25:370. doi: 10.1186/s12876-025-03961-5.
和文
- 菊池健太郎、藤岡ひかり、中原拓海、中野 湧、吉岡 慧、大谷津 翔、田中 剛、幸山 正。 発症に気象と地勢の関与が考えられた夏型過敏性肺炎の1例 日本病院総合診療医学会雑誌 2025;21:59-60.
- 中原拓海、菊池健太郎、原田真希、川合里奈、中野 湧、吉岡 慧、秋山真哉、梶谷真紀、田中悠太郎、藤岡ひかり、田中 剛、幸山 正。 成人肺炎患者におけるClostridioides difficile感染症の発症リスク因子の検討 帝京医学雑誌 2024;47:201-207.
学会発表(口頭・ポスターなど)
- 松本光太郎、足立貴子、渡邊彩子、綱島弘道、辻川尊之、阿曽達也、菊池健太郎、高橋美紀子。 EUS-FNB経験数からみたEUS下肝生検の肝組織収量の比較検討 ワークショップ13-12 肝硬変の新しい診断法とリスク評価 第110回 日本消化器病学会総会 2024年5月11日(アスティとくしま)
- 菊池健太郎、大﨑さゆり、田邉亜紀、黒﨑文広、茂木千代子、芦川鈴子。 当院のClostridioides difficile感染症例における酸分泌抑制薬の使用背景 第29回 日本病院総合診療医学会学術集会 2024年9月7日(有明セントラルタワー ホール&カンファレンス)
- 中原拓海、吉岡 慧、田中里奈、原田真希、石塚眞菜、梶谷真紀、秋山真哉、田中悠太郎、藤岡ひかり、菊池健太郎、田中 剛、幸山 正。 肺炎入院患者におけるClostridioides difficile感染症の発症リスク因子の検討 第261回 日本呼吸器学会関東地方会 2024年9月28日(秋葉原コンベンションホール)
- 菊池健太郎、松本光太郎、守時由起。 Clostridioides difficile感染症の発症と再発のリスク因子に関する調査研究 第28回 日本肝臓学会大会(JDDW 2024)ワークショップ5:肝臓・消化器領域における新興・再興感染症 2024年10月31日(神戸コンベンションセンター)
- 福井美音、美甘任史、高井敦子、南雲こずえ、竹内英之、内田大介、磯尾直之、菊池健太郎、原 眞純。 Klebsiella oxytocaによる敗血症性肺塞栓症を合併した1型糖尿病性ケトアシドーシス 第62回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会 2025年2月8-9日(ライトキューブ宇都宮)
- 松本光太郎、早川 淳、阿久津朋宏、岡本寛治、苗村佑太、菊山智博、齋藤 剛、足立貴子、渡邊彩子、辻川尊之、綱島弘道、勝倉暢洋、土井晋平、阿曽達也、高橋美紀子、菊池健太郎。 免疫チェックポイント阻害薬併用療法が奏効した切除不能肝細胞癌と表在型食道癌の重複癌の1例 第383回 日本消化器病学会関東支部例会 2025年2月15日(海運クラブ)